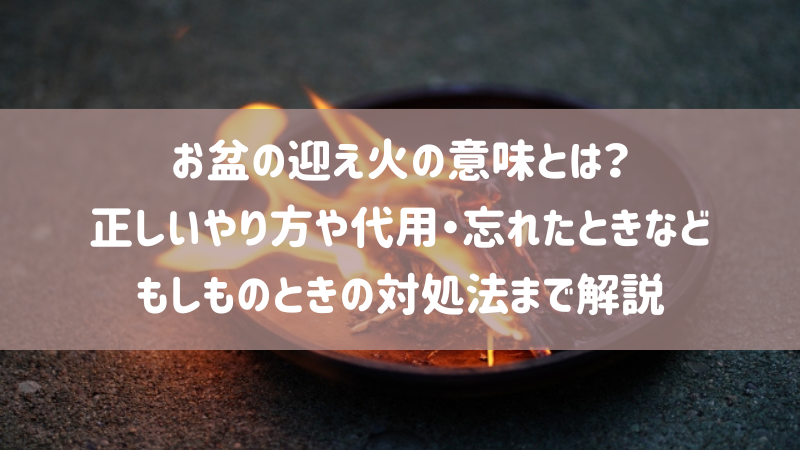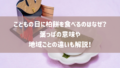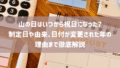「迎え火ってどうやって焚くの?」「場所は決まってる?」「火を使えないときはどうするの?」お盆の準備を進める中で、こんな疑問をお持ちではありませんか?

友達とお盆の迎え火・送り火の話をしてたんだけど、誰もどうやって焚くか知らなかった……
大切な行事だからこそ、正しく行いたいものですよね。この記事では、迎え火の意味ややり方に加え、代用方法や忘れてしまった場合の対応についても解説しています。気になるポイントをしっかり押さえて、ご先祖様を心からお迎えできるようにしましょう。
お盆の迎え火の意味と由来を詳しく解説
お盆の迎え火は、お盆の期間中に先祖の霊を家に迎えるために焚く火のことをいいます。この迎え火は、先祖の霊が迷わずに帰ってこれるようにするための道しるべとして灯される火なんです。
火は暗い道を明るく照らす役割があり、これによって霊が迷子にならずに帰ってこられるんですね。
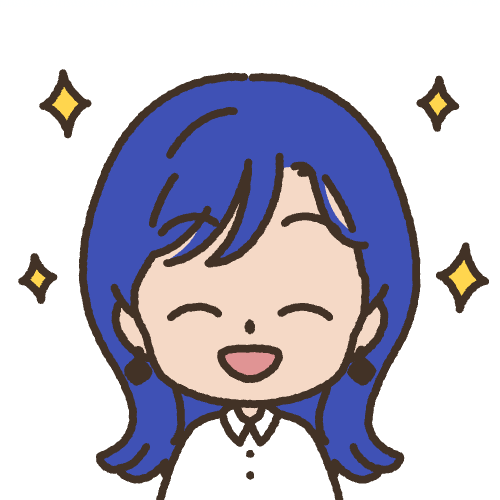
迎え火でご先祖様がおうちを見つけてくれるって、なんだか嬉しいですね。
迎え火で何を燃やす?適切な場所と正しい焚き方
お盆の迎え火は、玄関先や門の前など、家の入口で行うのが一般的です。火を使うので、まわりに燃えやすいゴミや枯れ葉がないか、必ず確認してから始めましょう。風が強い日は、特に注意が必要です。
迎え火で使うのは「おがら」と呼ばれるものです。これは麻の茎の皮をむいて乾燥させたもので、昔からお盆の迎え火に使われてきた材料です。おがらはそのままでは長いので、焙烙(ほうろく)という素焼きの浅い鍋の大きさに合わせてカットします。
次に、焙烙におがらを並べて、マッチやライターで火をつけます。火がついたら、ご先祖様が安心して帰ってこられるように、手を合わせて静かにお祈りします。
火が安定してきたら、迎え火の火を使って、盆提灯に灯をともします。これは、ご先祖様が家に入ってこられる時の目印になります。
おがらがすべて燃え尽きたら、しっかりと水をかけて火を完全に消します。火の始末はとても大事なので、最後まで気を抜かずに行いましょう。
そして最後に、盆提灯を仏壇の前など、ご先祖様を迎える場所へ移動させます。これで迎え火の流れが完了です。
迎え火を焚けない場合や忘れた時の代用方法と対処法
迎え火を焚きたくても、場所や事情によってできないこともありますよね。そんなときは、迎え火や送り火の代わりになるものを使っても大丈夫です。たとえば、ロウソクを使って火を灯したり、盆提灯を灯すだけでも、ご先祖様を迎える気持ちは伝わります。
電気式のロウソクや盆提灯を使う方法もあります。火を使わないので、安全に行えるのがいいところです。どうしても火が使えないときは、火をつけずに飾るだけでも、気持ちを込めることが大切です。
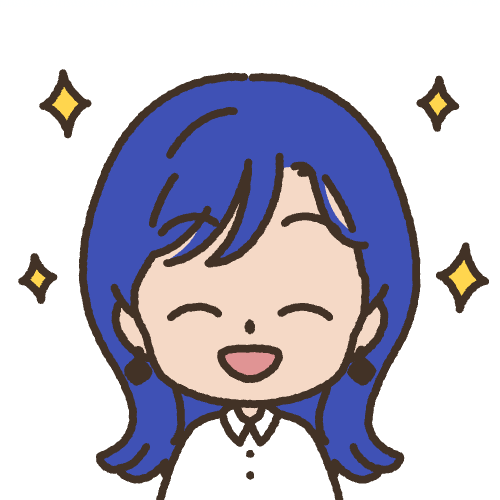
電気式なら、集合住宅や小さいお子様がいるおうちでも安心ですね!
また、うっかり迎え火を忘れてしまった場合でも、焦らずに。気づいたそのときにお墓参りに行ったり、お仏壇に手を合わせてお詫びするだけでも構いません。
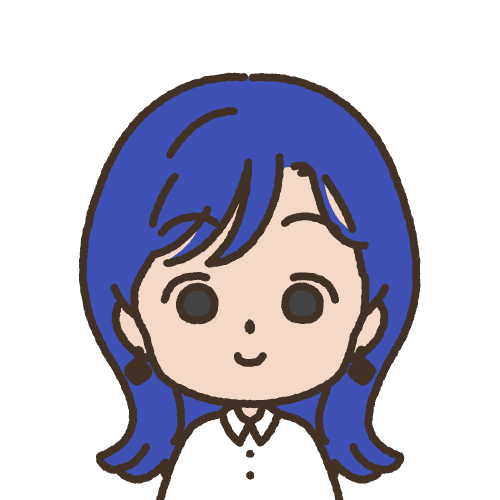
迎え火の形やタイミングが違っても、ご先祖様を思う心が何より大事なんですね。
まとめ
お盆にご先祖様をお迎えするための迎え火。昔ながらの方法に加えて、今の暮らしに合った工夫も取り入れられるようになってきました。どんな方法であっても、大切なのは「敬う心」と「感謝の気持ち」を忘れないこと。迎え火を通じて、ご先祖様とのつながりを感じられるこの時間を、ぜひ大切に過ごしてみてください。