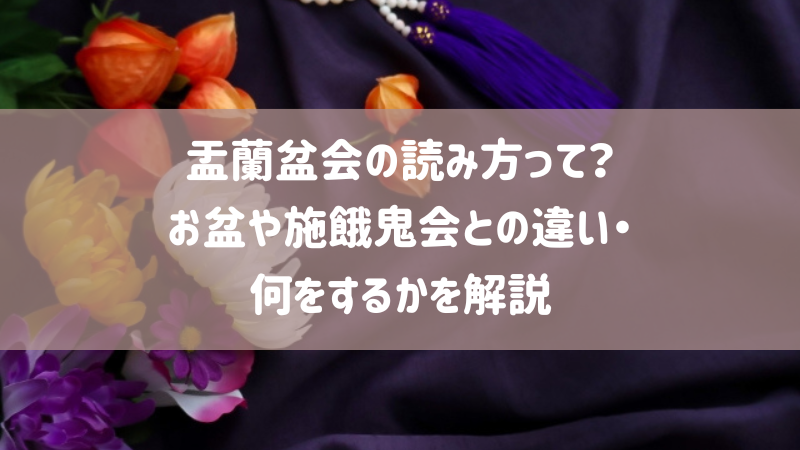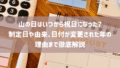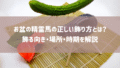「盂蘭盆会」という言葉の読み方をご存じですか?

8月によく見る気がするけど、う……うらんぼん……?
お盆とどう違うのか、また施餓鬼会との違いがよくわからない方もいらっしゃるでしょう。この記事では、そんな疑問をすっきり解消するために、盂蘭盆会の読み方だけでなく、その由来や期間、具体的な行事内容まで詳しくご紹介します。盂蘭盆会のことをもっと知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。
盂蘭盆会の正しい読み方とその意味をわかりやすく紹介
盂蘭盆会は、「うらぼんえ」と読みます。この言葉は、もともとサンスクリット語の「ウラバナ(urabana)」がもとになっていて、「逆さ吊りにされた」という意味があります。これは少し怖そうに聞こえますが、仏教の大切なお話が由来なんです。
仏教の経典『盂蘭盆経』には、目連尊者(もくれんそんじゃ)というお坊さんの母親が、死後に苦しい餓鬼道(がきどう)という場所で逆さに吊るされている姿が描かれています。目連尊者は母親を助けるために、一生懸命供養をしたそうです。これがきっかけで、私たちが今行っている盂蘭盆会の行事が始まりました。
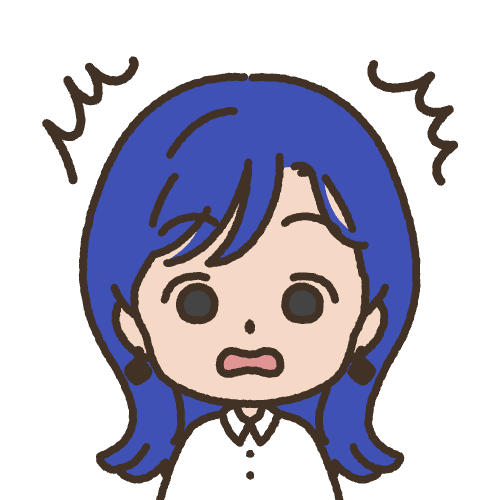
なるほど~!
……ん?それって、お盆と似たような行事ってこと?
盂蘭盆会とお盆・施餓鬼会の違いを比較して解説
実は、盂蘭盆会は「お盆」の正式な名前なんです。どちらも、ご先祖様の魂を自宅にお迎えして供養する行事や期間を指しています。ほかにも「精霊会(しょうりょうえ)」「盂蘭盆(うらぼん)」「盆供(ぼんく)」など、いろいろな呼び方があるんですよ。
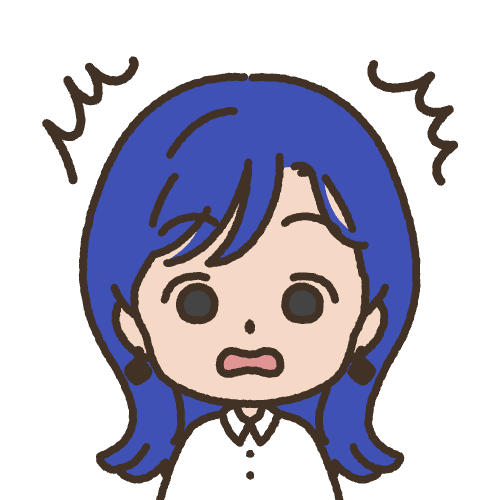
盂蘭盆会はお盆のことだったんだね!知らなかった!
次に、盂蘭盆会とよく混同されやすい施餓鬼会(せがきえ)について説明します。施餓鬼とは、餓鬼道という苦しい世界で飢えに苦しむ霊や、無縁仏と言って供養されない霊に食べ物を供えて供養することです。この供養を行うのが施餓鬼会です。
多くの寺院では、施餓鬼会は盂蘭盆会の期間中に行われることが多いので、同じ時期の行事として混ざってしまうこともあります。ただ、施餓鬼会はお盆の期間に限らず、いつでも行うことができる行事です。中には、毎日行っているお寺もあるそうです。
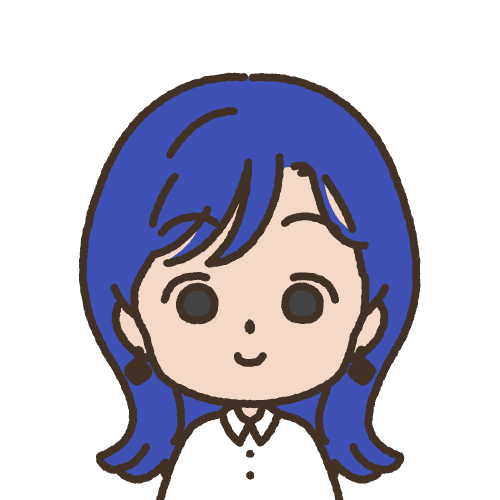
似たような行事に見えるけど、ちょっとずつ内容が違うんだね。
盂蘭盆会って何をする?いつからいつまで?具体的な行事内容
盂蘭盆会は、一般的には8月13日から8月16日までの4日間行われます。この期間は、ご先祖様の魂を家に迎え、そして送り出す大切な時間です。特に、13日は「迎え盆」といって、ご先祖様をお迎えする日、16日は「送り盆」として、ご先祖様をあの世へお送りする日とされています。ただし、地域によっては日程が違う場合もありますので、その土地の習慣に合わせることも大切です。
では、具体的に何をするのかを見ていきましょう。
まず、盂蘭盆会の前に、仏壇や仏具の掃除を行います。ホコリを払って線香立てや花立て、ろうそく立てなどをきれいに整えます。これはただの掃除ではなく、ご先祖様を心を込めて迎えるための準備なんです。
盂蘭盆会の期間には、迎え火と送り火があります。迎え盆の8月13日には、家の玄関や庭先で「迎え火」を焚きます。これは、ご先祖様が迷わず家に帰ってこられるように道しるべの火を灯す意味があります。逆に、送り盆の8月16日には「送り火」を焚いて、ご先祖様をあの世へ送り出します。京都の「五山の送り火」はその中でも特に有名で、山に大きな火文字が浮かび上がる壮大な行事として知られています。
そして、お供え物の準備も欠かせません。お盆の間、仏壇には季節の果物や精進料理、故人の好きだった食べ物などをお供えします。お菓子や飲み物も添えることがありますが、どれも心を込めた贈り物です。これを通して、故人との心の交流を感じられるのが盂蘭盆会の魅力だと思います。
最後に、お墓参りも大事な行事です。家族みんなでお墓に行き、草取りをして、墓石をきれいに拭きます。その後、花や線香をお供えして、静かに手を合わせます。
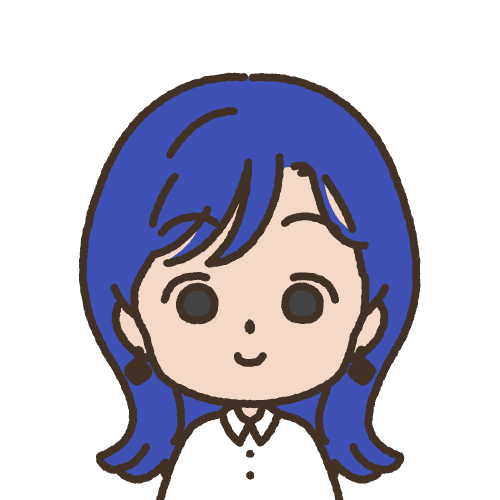
盂蘭盆会は、ご先祖様への感謝の気持ちを伝える大切な時間であり、なかなか集まれない家族の絆を深めるきっかけにもなりますね。
まとめ
盂蘭盆会(うらぼんえ)は、仏教の大切な教えに由来した行事です。ご先祖様を供養し、感謝の気持ちを伝えるために行われています。盂蘭盆会はお盆の正式な名前であり、迎え火や送り火を焚いてご先祖様をお迎えし、見送る期間でもあります。仏壇やお墓の掃除、お供え物の準備など、心を込めた行動がとても大切です。この記事を通して、盂蘭盆会の意味や行事内容を理解し、ご先祖様を大切にする気持ちを深めていただけたら嬉しいです。